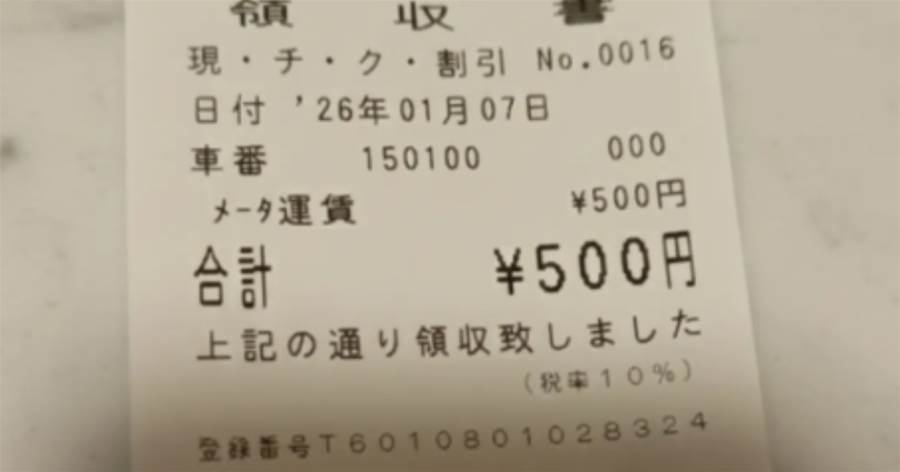

「そんな近距離でタクシー?歩けばいいでしょ。」
耳元で吐き捨てるように言われたその一言で、空気が一瞬にして凍りついた。
後部座席のドアを閉めたばかりの母の肩が、びくりと小さく跳ねるのが見えた。
駅から実家までは、たった600メートル。
歩けば十分もかからない距離だ。
でも、母はもう長い距離を歩けない。足を悪くしてからは、坂道を数分進むだけでも息が上がる。
だから私は、迷わずタクシーを拾った。
それなのに――。
運転手はバックミラー越しに私たちを見たまま、ため息をついた。
「はぁ……ワンメーターかよ」
小さく呟いたつもりなのかもしれない。でも、はっきり聞こえた。
母が慌てて頭を下げる。
「近くてすみません……足が悪くて……」
その声は、いつものように小さく、遠慮がちで、申し訳なさそうだった。
その姿を見た瞬間、胸の奥がじわっと熱くなる。
なぜ、謝る必要があるのだろう。
車は乱暴に発進した。
アクセルを強く踏み込んだのか、体がぐっと後ろに押しつけられる。
次の交差点で、今度は急ブレーキ。
母の体が前へ投げ出されそうになり、シートベルトが肩に食い込んだ。
「っ……」
小さな息を呑む音が聞こえる。
母は何も言わない。ただ、両手でシートの縁をぎゅっと掴んでいた。
その指先が、白くなるほど力が入っている。
運転手は何も言わない。
ミラー越しにちらりとこちらを見て、またため息をつく。
「近い客ってさ、一番面倒なんだよね」
ぼそりと、吐き出すように言った。
誰に向けた言葉かなんて、考えるまでもない。
母がさらに小さくなる。
視線を膝に落とし、かすかに震える声で言った。
「近いと……いつも嫌な顔されるの……」
その一言が、胸に深く突き刺さった。
――“いつも”。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください
引用元:,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















